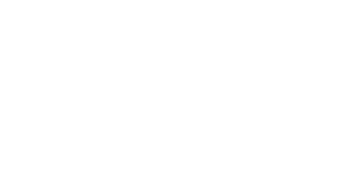-第3章- クリス・レッドフィールド
翌日の昼。
カフェに呼び出されたその男は、少し不機嫌そうだった。
「いったい何の用だ?」
挨拶の一言もなく、席に座ろうとする素振りも見せず、注文を聞きにきたウェイターも無視して、彼はそういった。
ダドリーはその唐突さに面食らいながら、席につくように促した。
だが、男は取り合わない。
「何の用だ? 俺をからかいたいなら、もっと暇なときにしてくれ。」
「落ちつけ。俺は聞きたいんだよ。お前の話を。」
ダドリーは席から立ちあがり、なだめるような口調で続けた。
「話っていうのはつまり、あのアークレイ事件のことだ。」
男はその"アークレイ事件"という言葉に明らかに反応を示した。一拍の間があって、無言のまま席につく。ダドリーも座る。存在を無視されつづけたウェイターは舌打ちして下がった。
「アークレイ事件か。あれについては署長に報告してるし、他の警官たちにも話したぜ。」
男の口調は素っ気無い。ダドリーは聞いた。
「俺は知ってのとおり、この3週間ほど謹慎を食らってる。おかげで詳しい話は知らないのさ。他の警官たちは面白おかしく脚色してお前の話を伝えるから、歪んだ情報しか入ってこない。だから、直接お前から聞きたいんだ。事件の真相を。」
男は苛立ちと諦めの混じった表情をした。男の報告が、他の警官たちからまるで信頼されていないことを、ダドリーは知っていた。
もちろん、彼も信じていなかった。
「なあ、頼むよ。クリス。お前の力になってやれるかもしれないんだ。」
一拍の沈黙があって、その男、クリス・レッドフィールドはゆっくりと口を開いた。
「アークレイで何が起きたか……もう一度説明しようか。」
連続猟奇殺人事件の解決を計ってアークレイ山地へと派遣されたSTARSは、そこで正体不明の怪物に襲われ、山中にあった1軒の豪邸に避難した。
だがその豪邸は、なにか邪悪な存在の住処だった。その住人は人肉を食う"動く死体"いわゆるゾンビであり、その他、おぞましい怪物たちが蠢いていた。その怪物たちの牙にかかり、STARSの隊員たちは次々に死傷していった。
しかし、クリスを始めとする生き残りの隊員たちは、怪物の襲撃を退け、豪邸を爆破して脱出することに成功した……。
「あらためて聞くと、なんだ。その……」
ダドリーは言葉に詰まった。
「荒唐無稽でとても信じられない、といいたいのか?」
静かな怒りを込めて、クリスが言葉をつなげた。ダドリーは首を振る。
「ああ、なんだ。その……お前の報告によると、アンブレラがこの事件に関係あるんだって? その話を聞きたいな。」
「アンブレラ……」
クリスの顔つきが一層険しくなった。アンブレラはヨーロッパで最大の……いや、世界で最大の製薬会社である。他の製薬会社が追いつけない規模の製品開発力を持ち、遺伝子工学の研究分野でも世界最高。各国の軍部とも取引があり、さまざまな治療薬を供給している。
華々しい功績の一方で、黒い噂もあった。中でももっとも頻繁に聞かれるのは、この会社が製品開発にあたって人体実験に手を染めている、というものである。また、疫病が流行したとき、それに対し有効なワクチンや抗生物質を開発するのに必要な期間があまりにも短いため、アンブレラ自身が意図的に疫病を流行させ、不当に利益を得ているのではないかという疑惑もあった。
問題の豪邸は、そのアンブレラ製薬の所有だったことがわかっている。クリスを始めとする生き残りのSTARS隊員は、そこで開発されていたウィルスによるバイオハザードがこの事件の原因であると主張していた。
しかし、アンブレラの発表によると、その豪邸は幹部クラスの社員が使用するレクリエーション施設として作られたものであり、研究施設として使用された事実はないという。館全体が老朽化しつつあり、事件当時は改築準備のために閉鎖されていたのであり、その内部に何者かがいたとすれば、それはアンブレラとは何の関係もない侵入者である。侵入者がそこを拠点として使用し、猟奇殺人を行っていたとすればそれは遺憾なことであり、管理責任を問われてもやむを得ない。しかし、殺人の責任まで負わされるいわれはない……。
STARS隊員たちは爆破された豪邸の跡を徹底調査することを申請したが、場所がアンブレラという大企業の私有地であり、調査費用もまた莫大であることから申請は却下された。
R.P.D内部で結成された事件調査委員会は、STARS隊員が動く死体と思っていたものは重度の麻薬中毒に犯されていた人々であり、彼らが猟奇殺人を繰り返していたと断じた。屋敷内を徘徊していたという怪物は、極限のストレス状態に置かれたSTARS隊員が見た幻覚に過ぎない、怪物などいるはずがない。これが調査結果であり、公式発表であった。
こうして、事件は幕が引かれた。
ほとんどの人々にとって、事件は過去のものとなった。しかし、その「ほとんど」の範疇に入らない人間がここに1人。
クリスはうめくように言った。
「間違いない。あの豪邸には大規模な研究施設があった。怪物がいた。そして、黒幕はアンブレラだった。俺は見たんだ。」
「……なるほど。」
相槌をうつダドリーの声には抑揚がない。
「クリス、俺はお前のいうことを信じようと思う。」
クリスが顔を上げた。ダドリーは続ける。
「だが、みんなにそれを信じさせるには証拠がいるな。何があればいいと思う?」
「あの事件のすべてのきっかけになったのはウィルスだ。」
「ああ、お前たちは署長にもそう報告したらしいな。」
「……豪邸の内部で見た資料には、Tというウィルスのことが書いてあった。このウィルスに動物が感染すると、身体が巨大化したり不死身に近い体力が得られたりするらしい。だが、脳細胞も汚染するから精神が破壊されてしまう。」
「そうなった人間がゾンビだっていうんだな?」
「そうだ。そのウィルスに関するアンブレラの内部資料が手に入れば、かなり有効な証拠になるはずだ。」
「内部資料……ね。」
アンブレラの内部資料。それを合法的に入手する方法などあるだろうか?
だが、もし手に入れば……それは大手柄になるだろう。
「そういうものがあるとしたら、どこにあると思う?」
「アンブレラの営業所や小さな支社をあたっても何もないだろう。末端の社員は何も知らないはずだ。だが、あの豪邸にあった資料の中には、ラクーンシティー内にある別の研究施設に触れたものがあった。もしその場所がわかって捜索できれば、何かが見つかるだろう。」
「どこか、か。それも漠然とした話だな。」
「おそらく、場所は巧妙にカモフラージュされているはずだ。薬品があっても誰も不思議に思わない大病院や、開発機材や薬品のような荷物を運搬しても不審に思われない倉庫、人が寄りつかない廃墟、そういう場所には手がかりがあるかもしれない。」
ダドリーは腹を決めた。
「クリス。俺に少しだけ心当たりがある。謹慎が解けるまでの6日だけだが、個人的に調べてみようと思う。」
「本当か?」
「ああ。何かわかったら、すぐお前に報告する。電話番号は変わってないよな?」
「変わってない。前と同じだ。もし俺が家にいなかったら、留守番電話に内容を吹き込んでおいてくれ。」
「わかった。」
「だが、気をつけろ。あの会社の闇には超法規的な何かがある。あの会社の警備員は普通のとは違う。見つかったら殺されると思ったほうがいい。危険だと思ったらすぐに逃げるんだ。」
「わかった。心配するな。俺の腕っぷしが確かなのはお前も知ってるだろう?」
「ああ。」
クリスは席を立った。仕事に戻る時間だった。彼がカフェのドアをくぐった直後に、ハリソンが店に入ってきた。
「なぁ、ダドリー。さっきクリスの奴にすれ違ったぜ。愛想笑いをしたら、思いっきり睨まれちまった。やれやれ。あいつは……」
「俺が呼び出したんだよ。」
「は?」
ハリソンの顔に怪訝な表情が浮かんだ。
「あ……何のために?」
「アークレイ事件のいきさつを聞いてみたんだよ。」
「アークレイ……お前ひょっとしてあいつの話を信じてるのか?」
「まさか」
ダドリーは笑った。
「ゾンビだの怪物だのを信じるほど、俺の頭はおかしくなってないぜ」
これは本音だった。ダドリーは最初からクリスの話を信じてなどいなかった。
「じゃ、何でまた?」
「直接話を聞いて見たかったんだ。奴が見たという怪物は、調査委員会が発表したように幻覚だろう。だが、アンブレラの話は興味がある」
ダドリーはウェイターを呼ぶと、コーヒーを注文した。ダドリーが驚く。
「またビールかウィスキーを頼むと思ったんだが。酒を止めたのか?」
「ああ。」
運ばれてきたコーヒーをブラックのまますすり、続ける。
「酒に逃げるのは止めだ。俺は何か大手柄を立てて、どん底から抜け出す。ジョアンナも呼び戻す。STARSなんか糞食らえだ。あいつらより、俺のほうがよっぽど優秀だってことを皆にわからせてやるのさ。署長から勲章の1つでももらってやる。」
「それで、どうするんだ?」
「クリスの話は話半分で聞いておくとして、だ。アンブレラに後ろ暗いことがあるってことは本当だろう。」
「なんでそう思うんだ?」
「アンブレラの私有地はどこも警戒厳重なのは知ってるだろ? あのアークレイにあったという豪邸だって、ただの麻薬患者が外部から入れるとは思えない……つまり……ゾンビと見間違えられた人間は、アンブレラの関係者だったに違いない。」
「アンブレラの社員に重度の麻薬中毒患者がいて、そいつが猟奇殺人の犯人で、それをアンブレラが隠蔽した、とか?」
「それは考えられるぜ。それとも、実は麻薬じゃなくて、アンブレラの開発した新しい薬が原因なのかもしれない。たとえば麻酔薬とかな。」
麻酔薬は一種の劇薬であり、処方を間違えると重大な神経疾患が起きることは知られている。もし、アンブレラ製の強力な麻酔が、被験者の精神を完全に破壊してしまったとしたら? 傍目にはゾンビのように見えるかもしれない。
「もし、アンブレラのスキャンダルの証拠を見つけることができたら、それは大手柄になる。そうだろう?」
「まぁ、そうだが……」
ハリソンが椅子の上で肥満体を揺すらせる。
「だけどなぁ、ブライアンはなんというかな。署長のブライアンのスポンサーはアンブレラだっていう噂だぜ。証拠を見つけても揉み消されるんじゃ……」
「そのときは、マスコミに発表してやるさ。手記を書けばベストセラー間違いなし。俺たちは国の英雄になれるぞ」
「能天気な奴だな……」
ハリソンはやれやれと首を振った。しかし、その表情はどこか嬉しそうだった。
彼の知っているダドリーは、楽天的で傲慢な自信家だった。そのダドリーが、数年振りに戻ってきたのだ。
ダドリーが声を潜め、ささやいた。
「ロバート・ジンジャーに、貸しを返してもらわなきゃな」
「ロバート……って、あいつか? アンブレラ営業所の所長の……」
「ああ、あいつならアンブレラの内部情報にアクセスできるはずだ。奴に頼んで、アークレイ事件の前後の時期に姿を消した社員をリストアップしてもらうのさ。」
「……お前、忘れてなかったんだな。」
「もちろんさ」
ダドリーは、口の端を吊り上げて笑った。
| 前ページ | 外伝TOP | 次ページ |