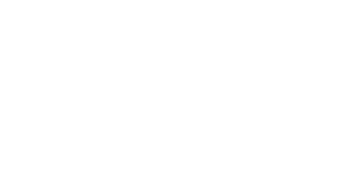-第1章- 堕ちた男
「あれをどう思う?」
ダドリーがたずねた。
「あれって?」
ハリソンが聞き返す。
晩夏の柔らかい陽光が刺しこむコーヒーショップ。すでに昼食時は過ぎ、店内は閑散としていた。その一角にあるテーブルに、ダドリーとハリソンは座っている。テーブルの上には、ハリソンの注文したコーヒーとハンバーガーの残骸、ダドリーが注文したミートパイと、空になったビールグラスが3つ。
窓から外を見れば、午後の仕事にかかるビジネスマンが足早にストリートを行き来する、ラクーンシティーの日常が広がっていた。
ハリソンは口ひげについたハンバーガーのケチャップをぬぐい、制服の胸元と、最近横方向への成長が著しい腹にケチャップがついていないことを確認した。
「"あれ"じゃわかんないだろう。お前は警察学校の時分からそうだが、言葉がたりない」
「STARSのことだよ。つい先日、例の連続猟奇殺人事件の捜査から帰ってきた」
「ああ、あれか。まぁ、なんというか……」
ハリソンは冷めきったコーヒーをすする。カップを空にして、どう答えたものかと躊躇する間があり、そしてこう答えた。
「信じがたい話だな」
「お前もそう思うか」
ダドリーは即座にそういった。その声には、予想通りの、そして当然の返事が返ってきたのに満足するかのような響きがあった。
ハリソンは不穏な雰囲気を感じて目を泳がせた。ダドリーはといえば、ぶつぶつと独り言をつぶやきながらビールジョッキをもてあそぶ。
「やっぱりもう1杯頼むか。……おい、ビールをもう1つくれ」
無愛想なウェイターがビールを運び、2人の席に置いた。年季の入ったグラスが木のテーブルに触れるか触れないかのうちに、ダドリーはそれをひったくるように手に取り、あおった。ハリソンは呆れ顔をした。
「ダドリー。お前、真昼間っからそんなに酒を飲むなよ。これでこの店に入ってから4杯目だろう? ジョアンナに逃げられてからってもの、会えばいっつも酔っ払ってるじゃねぇか」
「女房の話をするな!」ダドリーはジョッキを机にたたきつけ、泡を飛ばした。目が座っている。こうなるとこの男は人の話を聞かない。それを知っていたハリソンは首をすくめた。
「OK、オーケー、わかったよ。わかった」
いいながら首を左右に振るハリソンに、ダドリーは面白くなさそうな顔をする。ハリソンは話をそらすことにした。
「あー、なんだ。そのミートパイだが、ほとんど口をつけてないな。いらないなら俺がもらっていいか?」
「ああ、欲しけりゃ食え。」
「そうか。じゃあ。」
ハリソンはミートパイの一欠を口にほおばった。口にひろがる肉の旨みを味わいながら、感想を口にする。
「なんだ、結構いけるじゃないか。」
「いける? どこがだ? ジョアンナが作ったヤツに比べれば酷いモンだ」
しまった! 話を蒸し返しちまった!!
ハリソンは咀嚼途中のミートパイを喉に押し込みながら、心中で舌打ちした。ダドリーの妻の得意料理がミートパイだということをすっかり忘れていたのだ。
「えーっと、あー……さっきの話の続きなんだが……」
口元をいそいそと手でぬぐって取り繕う。
「で、なんだ。あのSTARSがどうしたって? ゾンビが現れたとか怪物と戦ったとか、そういう話だよな?」
「……ああ」
数ヶ月前からこの町・ラクーンシティーで頻発していた連続猟奇殺人事件。
数人で人間を襲って殺し、しかもその犠牲者の肉を食うというその事件は、全米のテレビや新聞をにぎわせた。どこかのカルト宗教団体が起こしたとか、獣化症に集団感染したグループによる犯行だとか、もっともらしい憶測が飛び交う中、RPD(ラクーンシティー分署)の署長ブライアンは、事件現場から類推して犯人が潜んでいると思われたアークレイ山地にSTARSを派遣した。
STARSはラクーンシティー内で起きるテロや災害など、さまざまな事態を想定して作られた特殊部隊であり、その構成員はRPD内外から広く集められていた。専門技能に長けた彼らなら、この前例の無い事件を解決する糸口を見出すのではないかと思われた。そして実際に事件は解決したのであるが……。
「事件を解決したっていっても、生きて戻ってきたのはたったの5人だっていうじゃねえか」
ダドリーはビールの泡を吹き出して息巻いた。
「やっぱり、あいつらには荷が重かったんだよ。俺みたいな現場叩き上げのヤツが必要だったんだ!」
それを聞いてハリソンはやれやれと首を振る。短い沈黙と溜息のあと、口を開く。
「ダドリー。いいかげんにしろ。お前がSTARSの選抜試験に落ちたのは、2年も前だ。もう忘れろ」
「なんだと?」
「お前が腕利きの警官だってことは、俺が知ってる。俺だけじゃない。RPDの現場で働いてる警官たちもみんな知ってる。謹慎処分が解けて現場復帰したら、STARSのことも、終わった事件のことも忘れて、真面目に警官の仕事をするんだ。いいな?」
「…………」
「ジョアンナだってじきに赦してくれる。きっと帰ってくるさ。じゃあ、俺はそろそろパトロールに戻るぜ。ああ、それから忘れるな。お前は謹慎中なんだ。あまり目立つ場所に出てくるんじゃないぞ。」
ハリソンは席を立った。そして帽子をかぶり、ふくよかな腹をゆすりながら店を出てゆく。
ハリソンの姿が完全に見えなくなってから、ダドリーは残ったビールを一気に飲み干し、うめくようにつぶやいた。
「くそったれ!」
| 目次 | 外伝TOP | 次ページ |